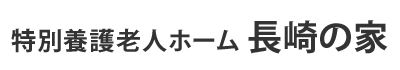令和7年度事業計画
基本理念
「やさしく・おいしく・清潔に」を基調の家庭的な雰囲気の中で、利用者の人格と命を尊重するために「食べる」営みを重要視し、経口・常食を実現できるよう栄養ケアマネジメントを通じながら豊かなホームでの生活の援助ができるよう努めていきます。
並びに利用者のお一人おひとりが、主体性を持った個人として尊重され、地域社会の中でご家族や近隣の皆様との交流を図りながら、生き生きとした生活が送れることを目指します。また、地域に貢献できるように、施設内で行っている「認知症予防」の学習療法等を用い「認知症予防教室」や「介護教室」を開き、地域社会の方々にも利用していただくようにし、社会との関係を拡大するように努めます。
上記実現のため、職員は法令遵守(コンプライアンス)と介護マニュアルを基本とし、柔軟にして積極的な先見介護を目指すとともに支援・援助行動を正確に記録し、事業を推進していくものとします。
社会福祉法人崎陽会・利用者権利擁護指針(コンプライアンスルール)
総合的な視点
- 私たち長崎の家の職員は、人が見ているときも、見ていないときも、いつも変わらぬ対応を行います。
- 利用者ひとりひとりの普通の生活(権利)を守ります。
- ひとりひとりの心身の状態や希望に沿った支援を行います。
- 認知症の方にも、子ども扱いせず、ひとりひとりの生活習慣を尊重し、希望やニーズに沿った対応をします。
- 自分で決めることが出来るようにお手伝いします。
- 金銭の取扱を明らかにします。
- 法令等を常に確認し、そのルールに基づいたサービス提供を行います。
| 身体の虐待 |
・排泄や食事等で失敗したときに、子供をしつけるようにたたく。 ・部屋や玄関に鍵を掛け閉込める。 ・介護服を着用させる。 |
| 経済的虐待 |
・買い物を頼まれお釣りを渡さない。 ・通帳を預かり、勝手に使う。 ・財産を勝手に処分する。 |
| 性的な虐待 |
・排泄等のことを回りに聞こえるように話す。 ・ワイセツな言葉で侮辱する。 ・性的な行動を強要する。 |
| 介護放棄~ネグレクト |
・オムツ、下着を濡れたまま放置する。 ・具合が悪いのに診察を受けさせない。 ・充分な食事を出さない、水分補給をしない、食欲がなく食べられない状態を放置する。 ・安全に過ごしているか確認しない。 ・汚れを放置する。 |
| 言葉・心理的虐待 |
・「なにやってるのよ」「汚い」「くさい」と怒鳴る。 ・その日の気分で対応を変える。 ・目でにらんだり、大声で威嚇する。おびえさせる。 ・返事をせず無視する。 |
認知症等で判断の難しい方に対しても介護してあげるという態度をとりません。以下の虐待行為を行いません。
私たち長崎の家の職員は利用者に対しても、家族に対しても、いつも同じく丁寧な対応、丁寧な話し方に努め、話をよく聞くことに努めます。
1.高齢者の虐待防止、身体拘束廃止の取り組み
利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の方法により利用者の行動の制限をしません。止むを得ず身体拘束を行う場合、様々な角度から拘束の必要性を検討した上で、ご利用者及びご家族に対し説明を行ない、相談員が承諾書を作成いたします。その後、3ヶ月ごとに行われる、サービス担当者会議の場にて、ご家族と共に、ご利用者の身体状態を確認・把握し、身体拘束の必要性や見直しを行います。
2.褥瘡予防マネジメントの取組
利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないように職員が基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて褥瘡発生の予防について配慮し適切な介護に努めます。
3.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行い、施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制の整備に努めます。
4.個人情報の保護
利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。施設が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることに努めます。
5.認知症予防の取組
初期の段階から最重度段階までの認知症高齢者の状態像を確認することや残存能力の把握を行い、介護する側が「どこに焦点をあてて、どのように介助したら良いか」を具体的にイメージするために脳の機能に着目し、現時点で医学的にわかっている範囲を基準にしたケアに努めます。
6.口腔ケアの取組
高齢者に多い誤嚥性肺炎の防止に取り組み、歯科医師や歯科衛生士の協力・指導の下、口腔ケアの向上に努めます。
7.重度化への対応(看取り介護体制の整備・推進)
重介護及び医療必要度の高い利用者のニーズに柔軟に対応すべく、夜間の緊急時にも看護職員がオンコール体制で待機し、協力病院との連携のもと、利用者の急変等に臨機に対応します。
又、「看取り介護の指針」を作成し、看取り介護の実践に努め、終末期を安心して施設で過ごせる体制を整備すると伴に職員の研修体制も整備します。
8.入所の受け入れ
優先順位名簿を基本に入所指針に沿ってご入所を受け入れていきます。
利用相談、施設見学
ご入所を希望される方に対して、入所申請を受けるだけでなく、ご入所されるまでの間、どのような介護サービスを受けるのが良いか、特別養護老人ホームに入所する以外の方法はないのか等、ご本人・ご家族の状況をお聴きしながら、ご相談をお受けします。また、ご利用前に施設の見学を勧め、ご利用者・ご家族が納得した上でご入所していただけるようにします。
新規入所者の受け入れ方針・評価基準・手続きの明記
これまでの「申し込み順」を改め、「介護困窮度・緊急度を重視」したものに、入所受け入れの考え方を変更します。 この指針に沿って、入所の評価基準・受け入れ方針を作成するとともに、その手続き等を明確にし、公表いたします。ご利用者本人の評価については、ご希望があれば開示いたします。
入所判定委員会
入所申請時の書面および介護支援専門員による訪問の結果を基に、新たなご入所者の受け入れを施設全体で調査します。入所判定委員会は、施設長、介護支援専門員、介護主任、看護主任、栄養士、生活相談員、事務長により構成しております。他、ご入所者を第三者的な立場から判断する、社会保険労務士により構成しております。
ご入所時から適切なサービスを提供
新たにご入所される方に対しては、ご入所時から適切なサービスが提供できるよう、入所前に訪問調査を実施します。介護支援専門員および看護職員、介護職員が、ご自宅あるいは入所・入院中の施設・病院を訪問し、ご本人のご意向や介護需要を把握するとともに、ご家族や入所・入院中先の職員から、必要な情報を聴き取ります。新規入所者の介護サービス計画は、ご入所前の調査結果を基に、当ホームの介護支援専門員が作成します。ご入所後は、この介護サービス計画に沿い、適切で安全な介護を実施するように努めながら、当ホームにおけるご利用者の様子をよく観察します。ご入所3か月後に、介護サービス計画の見直しを行い、新たな介護サービス計画を作成します。
9.介護サービス計画の作成
ご利用者の心身の状態と介護需要を把握し、ひとりひとりの介護サービス計画を作成し、その計画に沿ってサービスを提供します。サービス担当者会議の充実に努めるとともに、希望するご利用者やご家族がサービス担当者会議に出席し、意見を述べることができるようにします。
状態調査
ご利用者の心身の状態を把握するため、年に2回、ADL調査および認知症の状態調査を実施します。心身の状態に大きな変化がみられる場合は、その都度、調査を実施します。
サービス担当者会議と介護サービス計画の作成
個々の施設サービス計画は、MDS2.1-LAPSを使った方法により、計画担当介護支援専門員が作成します。
又、定期的なモニタリングを行い、サービス提供にあたり、他の従事者との連絡を継続的に行うことにより、必要に応じ又は‐定期間毎(概ね半年毎)にサービス計画の変更を行うものとします。
介護職員、看護職員、機能訓練指導員、管理栄養士、生活相談員、介護支援専門員、によるサービス担当者会議を開催します。サービス担当者会議では、ご利用者の介護需要を把握した上で、その需要を充足できるよう必要なサービスを検討します。
基本的に6か月ごとに一人ひとりの介護サービス計画を作成します。ご利用者に対するサービスは、この介護サービス計画に沿って提供します。また、それまで提供してきたサービスの評価を行います。
臨時サービス担当者会議
サービス担当者会議の内容を充実します。通常のサービス担当者会議に加えて、次の場合には、臨時サービス担当者会議を開催します。
①退院後等でご利用者の心身状態が大きく変化したとき
②試行の結果を基に計画を再作成するとき
③サービス担当者会議で決定に至らなかったとき
④早急に解決すべき問題が発生したとき
また、これに加えて、通常のサービス担当者会議で検討したサービス計画およびサービスの実施状況を点検・評価するとともに、通常のサービス担当者会議で決定できなかったこと、ご利用者に対するサービス提供のバランスの調整については、看護主任・介護主任が中心となり随時行っていきます。
介護計画の説明と情報の開示
ご入所契約時はもとより、ご入所後についても随時、介護サービス計画および介護サービス計画に沿って提供するサービスの具体的な内容をご利用者・ご家族等にわかりやすく説明し、同意を得た上でサービスを提供します。また、当ホームが作成した介護サービス計画の変更の申し入れも気軽にできるようにします。その際、ご利用者本人の情報が必要なときは、それを開示します。
10.日常生活介護
介護サービスは、ご利用者ひとりひとりの介護サービス計画に基づいて提供します。ご利用者の意思を尊重し、自立を支援するかたちで実施します。ご利用者の変化しやすい心身状況にあわせ、小さな変化も見逃さず、適切なサービスの提供に努めます。
排泄
排泄は、可能な限りトイレをご利用いただきます。そのために常にトイレの清潔の保持に努めるとともに、トイレ内にある手すりや緊急コールボタンを利用し、安心して快適に使っていただけるようにしております。また、個人の排泄パターンを把握するために排泄記録をつけ、ポータブルトイレや尿瓶、差込み便器等の活用、リハビリパンツ、尿取りパッドとトイレ誘導の併用により、極力おむつを使わない方向を目指していきます。また、適宜、排尿量を測定し、ご本人に合った尿とりパットの使用に努めていきます。おむつは、立位がとれない、尿意・便意が無い等、やむを得ない場合に限り使用します。定時のおむつ交換・トイレ誘導と排泄パターンが合わないご利用者に対しては、ご利用者の排泄パターンに合わせておむつ交換・トイレ誘導を行います。快適な排便、下剤にたよりすぎない排便を目標に摂取水分の調節や、下剤の削減などを行い、排便のサポートに努めていきます。
入浴
一般浴、機械浴の2種類の入浴方法を用意し、ご利用者の身体の状況に応じた入浴サービスを提供します。入浴日は、ご利用者1人当たり週2回を原則とし、ゆとりをもった入浴サービスを提供します。入浴できない方に対しては陰部洗浄・全身清拭・足浴を行い、着替えをします。季節行事一環として、5月に菖蒲湯、12月にゆず湯を実施します。
移動・移乗・体位変換
ベッド、椅子、車椅子、便器、浴槽等の間の移動・移乗は安全性を十分考慮し、ご利用者の身体の状況に合った方法で行います。また、杖、歩行器、シルバーカー等の補助具を有効に活用し、できる限り自立移動ができるよう援助します。
自分で寝返りをうつことのできないご利用者に対しては、褥瘡(床ずれ)を防止するために、体位変換の介助を行います。必要に応じて、クッション、エアマット、褥瘡予防シーツ等を使用します。
ご利用者ごとの最適な移動・移乗および体位変換介助方法をマニュアル化し、すべての職員が同じ方法で介助できるようにします。
口腔衛生
口腔衛生介助は、毎食後実施します。ご利用者の状態に合わせて、歯磨き、うがい、ガーゼによる口腔内の拭き取り、義歯の洗浄などを援助します。口腔衛生は、ご利用者の健康増進・維持に不可欠であるため、ご利用者の口腔衛生介助の充実を図ります。
整容(身だしなみ)
整髪、爪切り、髭剃り、顔剃り等を適宜行います。また、外出や行事の際には、ご要望により、お化粧やお洒落のお手伝いをします。
食事
食事に関しては、後述します。
介護用品の選定および衛生維持・安全点検
ベッド、エアマット、クッション、車椅子、歩行器、杖、介護テーブル、ポータブルトイレ、コールマット、入浴補助具等の介護用品ついては、使いやすさと安全性から選定し、その清潔の維持および安全点検に努めます。
11.ご利用者の日課
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00 | 起床・着替え・整容・健康体操 |
| 8:00 | 朝食・服薬・口腔ケア |
| 9:00 | 個別機能訓練 理美容(隔月曜予定) 入浴とシーツ交換(月・火・木・金のうち2日間) 自由時間 ⇒ クラブ活動(学習療法、ゲーム等) ★ベッド周りなどの消毒清掃(水) ★身の周りなどの清掃(土・日) |
| 10:00 | 喫茶開始 |
| 12:00 | 昼食・服薬・口腔ケア 自由時間 ⇒ お昼寝、クラブ活動(学習療法、ゲーム等) |
| 14:00 | 入浴とシーツ交換(月・火・木・金のうち2日間) 講師によるレクレーション(第1、第3金曜予定) クラブ活動(書道⇒土曜 創作⇒日曜)ミュージックベル(木曜) 喫茶開始 おやつ |
| 15:00 | ドクター回診(木曜日) |
| 16:00 | ★居室内キャビネットの整理(火曜日) 自由時間 ⇒ クラブ活動(学習療法、ゲーム等) ★ベッド周りなどの消毒清掃(水) ★身の周りなどの清掃(土・日) |
| 17:00 | 着替え |
| 18:00 | 夕食・服薬・口腔ケア |
| 19:00 | 自由時間 ⇒ TV鑑賞、お茶(お菓子の夜食) |
| 21:00 | 消灯 |
12.健康管理
ご利用者が健康で快適な生活を営めるよう、疾病の早期発見・早期対応に努め、生活の自立性を低下させないように援助します。
日常の健康管理
ご利用者の健康状態の細かな観察に努め、配置医師および協力病院等への連絡、職員間の情報交換を図りながら、健康維持に努めます。
定期健康診断
胸部レントゲン撮影、心電図、血液検査、尿・便検査、眼科検診、聴打診を、実施します。通院しての検査が困難なご利用者に対しては、すべての検査を施設内で実施します。
体重測定
毎月1回実施します。体重変化が著しいご利用者や、栄養状態のチェックが必要なご利用者に対しては、その都度実施します。
体温・血圧・脈拍等の測定
週2回の入浴時および体調に変化がみられたときは、その都度、体温、血圧、脈拍等の測定を実施します。
食事・水分摂取および排泄の把握
チェック表により、毎日、食事・水分の摂取量を把握します。摂食不良時は、医師の指示の下、看護職員、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員が連携して、その時々の状況に合った食事の提供、水分の補強を行います。便秘時には、排便コントロールを行います。
医師の診察および通院
週1回、配置医師(内科一般)が来診します。また、通院あるいは入院しての診療が必要な場合は、職員が付き添い、施設車両にて送迎をいたします。
口腔衛生
ご利用者ひとりひとりの口腔衛生介助の充実を図り、誤嚥性肺炎の予防等に努めます。
服薬
医師の診察の下、病状に応じ、ご利用者に服薬していただきます。
医療機関との連携
配置医師および協力病院等やご利用者のかかりつけ医との連携を密にし、日常の健康管理について適切な指示を得るとともに、緊急時の受け入れ先を確保します。(救急車を利用する場合、他の医療機関へ搬送される場合もあります。)
夜間緊急時の対応
看護職員が不在になる夜間・早朝帯のご利用者の容態の急変に対応できるよう24時間オンコール体制をとっています。
感染症等の予防対策
風邪やインフルエンザ対策として、ご来所者や職員に対して、うがいや手洗いの励行等の周知に努めます。11月には、希望するご利用者に対してインフルエンザ予防接種を実施します。高齢者施設で発生すると蔓延しやすい疥癬や食中毒等は、とくにその予防に努めていきます。また、感染症対策のマニュアルを作成します。
職員の健康管理
年1回(夜勤をする介護職員は年2回)の職員健康診断を実施するとともに、日々、職員の健康管理に努めます。
13.機能訓練
ご利用者の健康維持・増進を図るとともに、ADL向上や低下の予防のため、機能訓練指導員が生活リハビリを行います。また、ご利用者との信頼関係を築き、職員間での情報・意見交換を密にしながら、ご利用者の身体機能を回復することによって、利用者の生活の質の維持・向上を図ります。
レクやアクティビティを通しての訓練
レクレーションやアクティビティをとおして、可動域に対してストレッチ訓練を行い、できるかぎり柔軟な関節を保つようにします。必要に応じて筋力トレーニングを行います。
日常の動きの中での訓練
日常生活の動きの中で機能の回復を促します。
機能回復訓練
ご利用者のご希望、身体の状況に応じて、歩行、移乗、立位保持、座位保持等の訓練を行います。
その他
加齢により低下した生理機能を考慮し、嚥下体操、呼吸訓練、発声訓練などを行います。
14.食事・栄養管理
食生活の重要性を認識し、個人別に栄養ケアマネジメントを実施し、栄養バランス・味付け・調理方法等について、ご利用者ひとりひとりの身体的条件、嗜好等を配慮した食事を提供します。食事は、ご利用者が健康で楽しい生活を送る上でもっとも大切なものであることから、季節食・行事食も提供します。
食事の時間
食事時間は、朝食(08:00~09:00)、昼食(11:30~13:00)、夕食(17:30~19:00時)の間のご希望の時間帯にとっていただきます。
おやつは、15:00~15:30に提供します。
水分補給
食事時の他、午前10時と午後3時に、ジュース、お茶、紅茶などをご利用者の好みに応じて提供するとともに、常時、ケアセンターにお茶、お湯、水を用意し、ご利用者が自由に飲めるようにします。また、ご利用者が発熱している時などは、その都度、水分補給を行います。
食堂
離床を促すだけでなく、ご利用者同士の交流の場としての食事の機会を重視し、できる限り食堂やデイルームのお好きな場所で食事・水分補給をしていただきます。食堂及びデイルームは常に衛生を保持し、おいしく、楽しく食べていただく環境づくりに努めます。
メニューの掲示
刻み食、超刻み食、ミキサー食のご利用者にも食事の内容がわかるように、メニューの掲示を行います。
献立
献立は、ご利用者の希望を尊重するとともに、季節感を感じることができるものにします。また、定期的に行う嗜好調査や残菜調査(年2回実施、全体量は毎食)、聞き取り調査等の結果を分析し、献立の改善に努めます。また、毎食30分前に職員による検食を行います。
栄養管理
栄養管理上必要な平均栄養価は、ご利用者1日あたり、熱量約1400キロカロリー、たんぱく質60グラムを基準とします。過剰栄養に注意するとともに、不足しがちなビタミン、ミネラル、カルシウムの補給には特に配慮します。
食事の形態
ご利用者ひとりひとりの咀嚼・嚥下の状態に応じて、主食・副食は、複数の形態で提供します。主食(普通食、パン、全粥、7分粥、5分粥、3分粥、おもゆ、パン粥)、副食(常菜食、一口大食、小さめ一口、刻み食、超刻み食、ミキサー食、流動食)の他、代替食(ご入居者ひとりひとりの好き嫌いに対応する食事)を用意します。
食事の介助
食事は、原則的に全員が食堂で顔を合わせて召し上がっていただきます。ご利用者の体調不良の場合は、居室まで配膳します。ご利用者ひとりひとりの状態に応じた食事介助を行うとともに、残存機能を最大限に活用して、自助具等を使い、できる限り自力摂取できるよう援助します。
選択食
食事をさらに楽しんでいただくため、ご希望に応じ、主菜を選択食とします。選択食メニューについては、ご利用者ごとに聴き取り調査を行います。
行事食
敬老の日、元旦(おせち)、誕生会には、行事食を提供します。
ご希望に沿った食事
献立は、嗜好調査やアンケート調査等でご利用者からのご希望をお聴きし、なるべくご希望に沿うようにします。ご利用者の皆さんから希望があったものの、通常の献立に入れにくい料理等については、9月の敬老会や12月のクリスマス・忘年会のバイキング形式でのお食事の時に、可能な限り提供します。また、嗜好調査でご要望の多い寿司についても、バイキングにて提供いたします。
食器
食器ついては、ご利用者ひとりひとりの状態に応じて、食べやすい等機能的な理由のみならず、その形状・色合い等が食事の美味しさ、楽しさを引き立たせる重要な要素であることに配慮して選定します。
衛生管理
職員・出入り業者の衛生教育を徹底し、食品・調理器具、設備、建物の清潔の保持を図るとともに、二次感染の防止に努めます。また、万が一、O-157や食中毒等が発生した場合、その原因を速やかに究明できるよう、調理済み食品、食材料を-20℃で2週間以上冷凍保存します。
15.日常生活援助
ホームでの生活の充実を図るため、ご利用者ひとりひとりの生活状況に応じた援助を行います。
居室環境の整備
ご利用者の意向を尊重しながら、心身の状態、人間関係に配慮しつつ、各自が快適な居住空間を確保できるように努めます。居室については原則として6か月に1回の見直しを行います。さらに、介護の安全性を確保するため、必要に応じて居室の変更をします。
買い物の代行
ご利用者のご要望に応じて、週に1回、日用品の買い物を代行いたします。電池、ティッシュペーパー、歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、包帯、リント布等、需要の多い物品については、できる限り各人でご用意下さい。
ご無理な方は施設で代行いたします。
洗濯
日常衣類の洗濯を行います。
理・美容
頭部の清潔とお洒落を楽しんでいただくため、原則として毎月第2・4月曜日、理・美容師によるサービスを提供します。(ご利用者実費負担)
外出・外泊
外出・外泊については、心身の状況、外出・外泊先を考慮しながら、できる限りご利用者の意向に沿うようにします。
移送サービス
ホームからの通院のための送迎、施設行事実施時における送迎をいたします。
金銭管理サービス
ご希望がある場合は、現金、預・貯金の通帳、実印等の管理の他、ホーム利用料や公共料金等の支払い等を代行いたします。(預り金等取扱規程に基づき、利用料を負担していただきます。)
行政手続等の代行
ご利用者のご要望に応じて、杉並区等に提出する書類の代筆、申請の代行、郵便物等の投函等を、その都度、代行いたします。
要介護認定に関する代行
要介護認定の更新・変更申請をご利用者に代わって行います。
16.季節行事・余暇活動等
ご利用者に季節感を味わっていただくため、季節の行事を実施するとともに、音楽会、映画の日、クラブ活動等、趣味の活動の実施回数増や内容の充実を図り、ご利用者が自ら選んで楽しくご参加いただけるようにします。また、ご利用者に日々の生活のリズムを感じていただけるように、ホーム内放送、体操を実施します。地域との交流に力を注ぐとともに、地域の学校をはじめとする団体・個人によるホーム訪問を積極的に受け入れ、ご利用者の日々の生活をよりバラエティーに富んだものにしていきます。
音楽療法
週1回(木曜日)、音楽療法を実施します。意欲低下防止や残存機能の活用を目的に、専門指導員やボランティアと一緒に、音楽に合わせて楽器を鳴らし、歌います。
季節行事
行事や趣味の活動は、行事・レクリエーション委員会が中心になって企画立案します。行事やクラブ活動等については、実費相当分を負担していただく場合があります。行事やクラブ活動の具体的な日時や内容は、『沓掛だより』、ホーム内放送、館内のポスター掲示等を通じて、その都度、お知らせします。
4月-お花見
施設車両を使ってお花見に行きます。長時間の外出が困難なご利用者には、施設周辺の桜を楽しんでいただきます。
5月-端午の節句 菖蒲湯
五月人形を飾って端午の節句を祝います。菖蒲湯を楽しんでいただきます。
6月-喫茶店
お茶菓子を用意し、喫茶店の雰囲気を味わっていただきます。
7月-七夕
願い事を短冊に書き、笹の葉に飾ります。
8月-納涼祭
盆踊り、模擬店を楽しんでいただきます。ご家族、ボランティア、地域の皆さんとともに暑さを吹き飛ばします。
9月-敬老会 運動会
健康と長寿をお祝いし、お食事は特別食をご用意します。玉入れやボールを使ったゲームなど、スポーツを楽しみます。
10月-おくんち
おくんち見物に出かけます。また出かけられない方の為、小江原保育園の園児によるおくんちの出し物を施設内で行います。
11月-文化祭
クラブ活動等の作品を館内に展示します。
12月-ゆず湯 クリスマス 忘年会
寒さや風邪に負けないようにゆず湯で温まります。館内にはクリスマスツリーを飾り、ご家族、ボランティア、地域の皆さんと一緒に、一年を締めくくり、新しい年の皆さんの健康・長寿を祈ります。お食事はバイキング形式で実施します。
1月-初詣
飾りつけ等を行い、新年を過ごしていただきます。ご希望者に対して職員等が付き添い、近くの神社まで初詣に出かけます。
2月-節分
災いを追い払い、福を呼び込むために、豆まきをします。
3月-ひなまつり
ひな人形を飾り、春の到来を喜びます。
誕生会
月1回誕生者の長寿をお祝いする会を行います。ホームからはささやかなプレゼントがあります。
クラブ活動・趣味の活動
書道クラブ、手工芸クラブ、編み物クラブ)、生け花クラブ、カラオケ(週1回))を実施します。クラブ活動等への参加が難しい方に対しては、リラクゼーションプログラム(少人数で、手や足のマッサージ、簡単な運動等を行う個別プログラム)を実施しています。クラブ活動や趣味の活動は、ボランティアの方の活動希望を調整しながら、ご利用者のご要望を聴き、回数増と質の向上を目指していきます。
行事等のお知らせ・掲示板の設置
ご利用者に日々の生活のリズムを感じていただけるように、毎日、朝・昼・夕にBGM放送を施します。行事・クラブ活動およびご利用者の誕生日については、毎月、各階に掲示します。その他の大きな行事、風邪や食中毒の予防への協力について等のポスターは、その都度、館内に掲示します。
外出の援助
ご利用者のご要望に応じて、お花見や初詣等、行事で施設から外に出ていただく回数および対象者を増やすとともに、ボランティアやご家族の協力を得ながら、近所への散歩や買物の外出の援助に力を注ぎます。
面会・訪問活動等の受け入れ
ご家族やご友人のご面会を歓迎します。警察学校、小江原保育園をはじめとする地域の学校等、個人や団体による訪問活動・ボランティア活動を積極的に受け入れ、ご入所者との交流の充実を図ります。また、来所しやすい雰囲気づくり・環境づくりに努めます。
17.相談活動、要望・苦情相談窓口、ご利用者の集い、家族懇談会等
ご利用者やご家族からの相談には、その都度対応し、ご利用者が安心して生活できる環境づくりに努めていきます。日々の相談業務を強化するとともに、『要望・苦情相談窓口』を、ご利用者やご家族にとって気軽に利用できるよう、工夫していきます。
個別相談
ご相談の内容に応じて、おおよそ以下の職員が対応します。
①管理運営上の相談…施設長、事務長
②処遇上の相談…介護支援専門員、生活相談員、介護主任、看護主任
③健康上の相談…医師、看護主任、機能訓練相談員
④食事・栄養管理上の相談…管理栄養士
⑤入退所時の相談、その他の相談…生活相談員
要望・苦情相談窓口
日常の相談とは別に、とくにご要望・苦情に関しての窓口を設け、サービスの向上と改善を図ります。
①苦情受付担当者(介護支援専門員)がご要望・苦情の受け付けの窓口となり、その相談に応じます。受け付け窓口を生活相談員以外としたいときは、苦情解決責任者(施設長)に申し出ることができます。お申出は、口頭、電話、文書のいずれの方法でもできます。また『ご意見箱』へ投函していただいても構いません。(『ご意見箱』は、施設長しか解錠いたしません。)
②苦情解決責任者(施設長)は、苦情受付担当者の報告を受け、職員を指揮し、施設全体で、ご利用者・ご家族等からのご要望や苦情に対して誠意を持って対応し、その解決や改善に取り組みます。
③苦情解決責任者は、苦情申出者に対し、1か月以内に改善(検討結果)の報告を行います。1か月以内に改善(検討結果)の報告ができないものについては、検討状況の報告を行います。
18.環境美化、事故防止、防災対策
ご利用者が安全、かつ快適に生活できるよう、建物設備等の維持管理、清潔保持、美化運動、転倒・ベッドからの転落等の事故の防止、容態急変時等の緊急対応の迅速化、および防災対策の充実に努めます。
建物設備等の維持管理
建物設備等を清潔、快適性、利便性、安全性の視点から常に点検し、その維持管理、改善に努めます。
清潔保持、美化運動の推進
環境美化委員会を中心に、ご利用者が安全、かつ快適に生活できるよう、居室・食堂・廊下・浴室等の施設・設備、テーブル・椅子・介護用品等の備品類、ご利用者・職員の衣類・ユニフォーム・布団等の清潔保持に取り組んでいきます。また、備品等の整理整頓に努め、バルコニーや敷地内の花壇等に花を植えるなど、美化運動を推進します。
事故の防止
ご利用者の転倒や、ベッドからの転落等の事故を防止するため、居室、食堂、廊下等の環境整備、またベッド、車いす等の介護機器の安全点検・整備を行うとともに、職員による見守りの強化を図ります。また、サービス向上委員会を中心に、これまでの事故およびその原因を分析し、事故防止と、見守り強化の観点から夜間の巡回を増やします。
防災対策
防災対策・緊急対応の体制 防災機器の定期的な点検を行うとともに、災害時に迅速かつ冷静な判断、行動ができるよう、消防署の協力を得ながら、月1回の防災訓練を実施します。防災訓練は防災委員会が中心になって企画し、このうち2回は総合訓練として通報、消火、避難訓練を実施します。災害時に備えた地域の団体等との連携など、防災対策を強化します。また、警備を兼ねた宿直員を設置し、特に夜間帯の防災・緊急対応の体制を強化します。
非常食の確保
非常食等の確保 災害時等の非常時に備え、ご利用者1人あたり3日分の非常食と飲料水(9リットル)を常備します。また、救急セット(包帯、三角巾、絆創膏、脱脂綿、はさみ、とげ抜き、ピンセット等)が入った非常用持出袋を医務室に配備します。
緊急対応
ご利用者の容態急変時等の緊急対応が的確かつ迅速に行えるように、緊急時対応のマニュアルを作成し、全職員への徹底を図ります。
避難時の人員確認に使用する避難者名簿を作成します。
19.記録・会議・研修等
介護職員、看護職員、機能訓練指導員、管理栄養士、生活相談員、さらに事務職員も含めて、それぞれの担当職員が一致団結してサービスを提供していくために、記録、申し送り、会議を充実させていきます。ひとりひとりの職員の資質の向上を図り、責任を持って職務に従事できるよう、各種の研修を実施します。また、職員のマナーの向上に努めます。
介護サービス記録
ご利用者の日々の心身状況を把握し、ご利用者に対して必要な介護・看護サービスが提供できるよう、介護・看護に関する以下の介護サービス記録を整備するとともに、その記録の充実・活用に努めます。
①介護ケース記録…ご利用者一人ひとりの日々の心身状況、ホームでの生活のご様子について、介護職員が記載します。
②看護ケース記録…ご利用者一人ひとりの日々の心身状況について、とくに医療面に関して、看護職員が記載します。
③介護日誌…その日に行った介護サービス全般について、介護職員が記載します。
④看護日誌……その日に行った看護サービス全般について、看護職員が記載します。
⑤各種チェック表…排泄、食事・水分摂取、入浴、爪切り、クラブ活動の参加状況等について、介護職員が記載します。
ご利用者は、いつでもご自分の介護サービス記録の閲覧を求めることができます。
申し送り
毎日申し送りを実施し、ご利用者の直近の状態およびサービスの具体的提供方法について確認と点検を行います。ご利用者の介護・看護に関する最新の情報が職員間に漏れなく的確に伝達されるよう、申し送りの内容の充実とともに伝達技術の向上に努めます。
サービス担当者会議
月に1回、各部門の責任者により、施設全般にわたっての事業運営の検討、サービスの実施状況の確認と点検を行います。
研修等
介護保険施設の職員として、ひとりひとりの職員が、責任を持って職務に従事できるよう、日々の業務を通じての職場内研修により、その資質の向上を図っていきます。専門的な研修については、長崎県や市、社会福祉協議会等、外部機関が実施する研修を受講させ、職員のレベルアップを図っていきます。
事業評価
長崎の家のサービス、職員の資質の向上を図るため、前年度の事業評価をします。
職員のマナーの改善・向上
ご利用者やご家族に対する言葉遣いや接し方等、職員のマナーの改善・向上に努めます。全職員が名札を着け、ご利用者、ご家族、来所者に職員の名前がわかるようにします。苦情をいただいた際は、施設長から全職員に対して、その都度、文書および口頭にて教育・指導・注意を行います。
20.施設の公開、地域相談活動、地域との交流等
地域の皆さんに当ホームを公開し、ホームへの理解・関心の向上を図り、福祉意識を醸成していくとともに、気軽にご相談いただける態勢をつくります。
21.ボランティア受入れ等
Ⅰ.受入れについての基本的な考え方
①施設の社会化を目指す
②福祉教育、ボランティア体験の場の提供
③提供サービス及び利用者の生活の質の向上
Ⅱ.活動内容
①日常生活に関わる活動
・間接的ふれあい活動(洗濯物たたみ、清拭用品作り等)
・ふれあい活動(話し相手、入浴後のドライヤーがけ)
②行事や日常プログラムへの参加
・趣味、レクレーション、クラブ活動への参加
・ふれあい喫茶への参加、手伝い
Ⅲ.活動の発展と持続性の確保に対しての活動
①専門的機能の提供
・車椅子操作に関する指導
・介護者教室との連携による介護、介助技術指導
②ボランティアと施設側との十分なコミュニケーション経路の維持
・ボランティア懇談会の開催
Ⅳ.学生ボランティアの受け入れ
①ボランティア経験を通じて、施設や利用者への理解を深めてもらうとともに、ボランティア育成を目指す
②活動終了時、担当職員と反省会を行う(ボランティア活動の記録に活動経過、内容、反省等記入して貰う。
Ⅴ.ボランティア受け入れ方法
①事前面接
・希望内容の確認
・施設概要及び施設見学
・活動内容の紹介
②活動当日のオリエンテーション
・タイムテーブルの確認
・活動にあたっての注意点、ボランティアのしおり、来設簿等の説明
・ボランティア保険の紹介
・ボランティア登録書記入